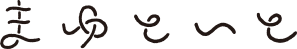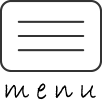皆さんの住む地域には、昔から大切にされている神社はありますか?家族と一緒にお参りをしたり、ここぞという時にお願い事をしたり…
富岡市では貫前神社や妙義神社が有名ですが、市内には多くの神社が点在しています。私カネコも、子供の頃に毎年お参りをしていた神社がありました。でもその神社の歴史を、今までよく知らなかったことに気づいたのです。
今回はその神社の歴史と、地域の人たちとの関わりを調べてみました。

「雷電様」まで歩いてみよう!
その神社は、岡本地区の中でも上岡本区と呼ばれる地域にある『雷電神社』です。毎年5月5日に例大祭が開かれ、地域の人からは「雷電様」と呼ばれ親しまれています。
雷電神社があるのは、なんと山の上。 山と言ってもそれほど高くなく、ちょっとしたハイキング気分でお参りできる場所にあります。私はしばらく行っていなかったので、今年のお祭りの日に久しぶりに登ってみることにしました。
しっかり準備運動をして、山の上の神社へレッツゴー!!

神社へ向かう道の入口がどこにあるかというと、なんと『野生の王国・群馬サファリパーク』の駐車場にあります。富岡市民にはとても身近な動物園ですが、神社の存在には気づいていない人も多いのではないでしょうか。
サファリパークのゲートに向かってトンネルを通過し、第2駐車場の看板に従って右に曲がると、その駐車場の片隅に赤い鳥居が見えます。そこが雷電神社へ続くの道の入口なんです。
 第2駐車場を目指して道路を曲がると、左手に鳥居が見えます。
第2駐車場を目指して道路を曲がると、左手に鳥居が見えます。
鳥居をくぐると、緑の木々に囲まれた山道になります。少し傾斜がきつい箇所もあるので、足元を確認しながら慎重に登っていきます。
お祭りが行われる5月は新緑が綺麗で、ハイキングにちょうどよい季節。深呼吸しながら歩くと、とても気持ちがいいですよ。
 天候によっては滑りやすい所もありますのでご注意ください。
天候によっては滑りやすい所もありますのでご注意ください。
道が狭い所もあるので、すれ違う場合は慌てず、譲り合うようにしてください。階段が整備されていたり、手すりが設置されている所もありますが、時間の経過で劣化している箇所もありますので、十分に注意してくださいね。

しばらく登っていくと、岡本地区を見下ろせる場所に出ました。ここまでそれほど時間は掛かっていませんが、景色を見るとなかなか高い所まで来たことがわかります。
「ゴールまであと一息」の看板に励まされて最後の階段を上がれば、神社へ到着です!

 この階段を上がると社殿に到着します。
この階段を上がると社殿に到着します。
鳥居からここまで15分ほど。ハイキングとしては、ちょうどいいコースではないでしょうか。
到着すると、雷電神社の社殿があります。社殿の周りは整備され広くなっているので、ここでひと休み。5月はツツジが咲きとても綺麗でした。

太鼓があったので叩いてみると「ドーン」と音がとても響きました。登った記念にこの太鼓を叩くのが流儀なのかもしれません(笑)。

神社の歴史を知りたい!
社殿を眺めながら休んでいると、いくつかの疑問が湧いてきました。
・雷電神社はなぜこんな高い所にあるのだろう?
・やはり雷様を祀っているのかな…
・いつからこのお祭りは始まったのだろう?
子どもの頃は毎年当然のようにお参りをしていた私。でも何も知らなかったのです。
そこで、神社総代を務める宮下和夫さんに、雷電神社の由緒について聞いてみました。

― 地域の人達が大切にされている雷電神社について教えてください。
宮下さん:それがね、この神社については私たちも、先代の人たちからあまり聞いていないんですよ。しかも、この神社の由緒が書かれた物はほとんど残っていないんです。このお祭りは代々受け継がれてきているものですが、神社の由緒を正確に知る人は今はいないかもしれません…。ただ昔聞いた話では、近くにある『西方寺』や『額部神社』に関係しているのでは、と聞いたことはあります。
…なんて謎めいた神社なのでしょう。
毎年お祭りが行われ、大事にされてきた雷電神社をこのままにしてしまっては申し訳ない気持ちになり、私は図書館で資料を借りて調べてみることにしました。
また、宮下さんからいくつか資料をお借りすることができたので読んでみると、少しずつ雷電神社について解ってきたのです。
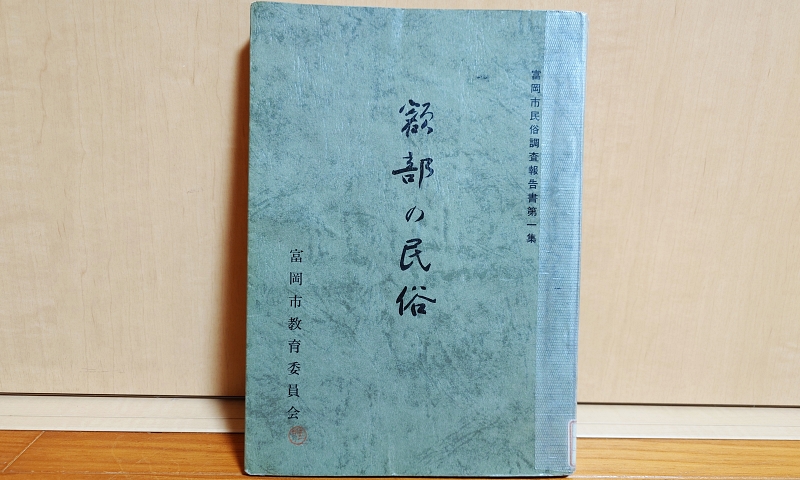 参考文献:富岡市教育委員会「富岡市民俗調査報告書第一集 額部の民俗」
参考文献:富岡市教育委員会「富岡市民俗調査報告書第一集 額部の民俗」
調べたことを要約すると、
“寛政年間に能登山のナガイワ神社から現在の地に雷電神社になったもので雷様をまつる。もとは七日市藩に所属していたもので、七日市の殿さまがまつった。その際は西方寺の義超法印によって勧請された。その後、明治42年に南後箇・岩染・岡本にあった神社が合祀され「染箇岡神社」となり、さらに明治45年に野上の神社も合祀され「額部神社」となった。
合祀の際、雷電神社の社殿は取り壊されたが、跡には石宮と奥の院が残されていた。その後大正8年に地元の有志によって新たに社殿を建て、雷電神社の復興と祭日の復活が行われるようになった。”
とありました。
寛政年間にこの地にまつられた雷電神社は、明治時代に国が行った神社の合併政策により、一度なくなっていたのです。そして額部地区にあった複数の神社が一緒になり、額部神社となったとのこと。(現在、額部地域づくりセンターの前にあります。)しかし数年後に、地元の人々の手によって雷電神社が復活していたのですね。
それから現代の今までこの雷電神社は、地域の人たちによって大切に守られてきたのです。今となってはなぜ神社が山の上に建てられたのかはわかりませんが、七日市藩のお殿様によってこの地が選ばれたのかと思うと、特別な気持ちになりました。
ただ資料にあった「能登山のナガイワ神社」については資料にも詳しい記載はなく、またインターネットなどで検索してみましたが、全く分からないままです。
 社殿から少し離れた場所に奥の院があります。かなり急な斜面ですので十分に気をつけてください。
社殿から少し離れた場所に奥の院があります。かなり急な斜面ですので十分に気をつけてください。
また資料にはこんな言い伝えもありました。
“お祭りでは獅子舞が奉納される。雷電様は獅子舞が嫌いだと言われ、雨乞いの時に獅子舞をふると怒って雨を降らせるのだという。また、雷電様には馬のくつ(わらじ)が奉納されていて、これを借りて掃立のときに蚕室に飾ると蚕が当るという。”
養蚕が盛んだった頃の富岡の人々の願いがあったのですね。
これらの情報を手に、再び宮下さんを訪ねました。
― 一度はなくなっていた神社ですが、上岡本区の人達で復活されていたのですね。
宮下さん:この地域では昔は養蚕が盛んでしたから、桑畑がたくさんありました。お米を作る農家も多く、田んぼもたくさんありましたね。それで雨を降らせてほしいと雷電様にお願いしたのでしょう。
上岡本地区の人たちにとって雷電神社は、大切な心の支えだったのかもしれません。
受け継がれることと現代の思い
地域の人たちの願いで復活した雷電神社は、100年以上の時を経てもなお、大切に受け継がれています。

― 復活から長い年月が経っていますが、現在ではどのようなお祭りをしていますか?
宮下さん:昔は祭日は寅の日でしたが、今では5月5日がお祭りの日です。準備は前日から行なっていて、朝から当番の人に出てきてもらい、午前中にお札を作ります。今でも版木を使ってお札を作り、希望者には有料でお配りしているんです。昔ながらのお札作りは手間がかかりますが、こうして作り続けられるのは地域の皆さんのおかげです。そして午後には地域の他の方々にも出てきてもらって、登る道を整備したり、社殿を開いて綺麗にしたり、旗を立てて太鼓を出したりして、お祭りの準備をします。だからお祭りは2日がかりなんですよ。
― こんなに長く続けられてご苦労もあるのではないですか?
宮下さん:祭日が5月の連休中ということもあって、お祭りに参加しづらいという話も聞きますし、年々参拝者は減ってきています。昔は就職や結婚などで家を出た人たちも、お祭りの日には帰ってきて家族で雷電様へ登ったり、家で揃って食事をしたりと、各家庭でお祭りならではの雰囲気がありました。最近はそういったことも少なくなって、ちょっと寂しいですね。
私も子供の頃は毎年「雷電様」に登っていました。両親が忙しそうにお祭りの準備をしているのを見て、連休とお祭りの雰囲気にワクワクしていたのを思い出します。
現在でも前日から準備されていて大変なことも多いかと思いますが、地域に大事にされている雷電様を、これからも守っていってほしいと願っています。
皆さんも、自分が育ってきた場所や今住んでいる場所の歴史を巡ってみませんか?
富岡市では市内の文化財をめぐる「ふるさと歴史ウォーク」を過去に行っており、その時の資料をホームページで紹介しています。読んでみると、新たな発見があるかもしれませんよ。
⇒ ふるさと歴史ウォークの過去の資料を掲載します | 富岡市
※紹介している史跡の場所は私有地の場合もありますので十分にご注意ください。
※総代様からの情報と資料を参考に記事を作成しましたが、この件に関しては様々な言い伝えがあることを追記いたします。
いかがでしたか?今回は、地域の人たちにもあまり知られていなかった雷電神社の歴史を残すことができればと思い、総代の宮下さんにもご協力いただきました。上岡本区出身の人や今もそこで暮らしている人たちに、「当たり前のように思っていた神社にこんな歴史があったんだ」と知ってもらえたら嬉しいです。
また現在の社殿は、昭和61年に改築されています。多くの木材などを山の上まで運ばなければ建てられなかったのですから、改築工事に携わった当時の人々は大変なご苦労をされたと思います。お参りをする際には、そんなことにも思いを巡らせてみてください。
皆さんにも、大切にしていきたい地域のお祭りや行事はありませんか?
ぜひその思いを、まゆといとに届けてください。
(カネコ)